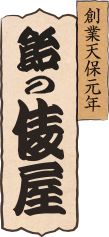穀物から甘味を得る事を知りえた先人の知識には、とても驚きと感銘を受けます。砂糖がとても貴重で入手が困難な時代、庶民の甘味料として生み出された麦芽糖は、麦芽の酵素が米のでんぷん質を糖化させるという知識と、経験に裏打ちされた製造方法で優しく自然な甘味を穀物から作りだしました。
そんな俵屋のじろあめは、お客様のお目にかかるまでに約4日間の日数を必要としています。
①
まず、お米を十分に洗い大きな桶の中に入れます。水を張り水分を十分に吸収させるため、翌朝に掛けて数回水を変えながら一晩寝かせます。

②
翌朝、一晩寝かせて水分を含ませたお米を蒸し上げ、大麦の芽(麦芽)といっしょに混ぜ合わせ、適量のお湯と共に糖化を促します。






③
釜に入れるお米と麦芽の層が上部と下部とが均一になるように、ゆっくりと滑らかに混ぜ合わせます。
④
数時間後釜の中のお米の糖化具合を確認します。その時の温度管理と、麦の良し悪しにより糖化の進み具合が変わり緊張の工程です。
⑤
一定の糖化を得ると、次は米・麦芽の抜け殻と糖化液とを分離させるために、大きな圧力盤の隙間に送り込み搾り出し、一晩寝かせて落ち着かせます。
⑥
3日目に入ると糖化液を蒸発釜に送り炊き上げ、水分を蒸発させていくことにより徐々に水飴らしくなっていきます。







⑦
水飴を仕上げの釜に移します。季節ごとに水飴の堅さを調整しているため堅さを決める蒸気を止めるタイミングが一番難しく熟年の目が必要となります。
⑧
複数の釜から、ほぼ完成した水飴を杓で「船」(飴を一時貯える大きな容器)に集めてかき混ぜ、より均一の堅さにします。
⑨
さらに出来上がりから一晩寝かせることにより、伝統の味「じろあめ」が完成します。
⑩
出来上がった「じろあめ」が店頭に並びます。